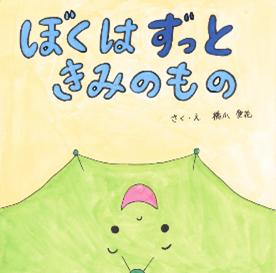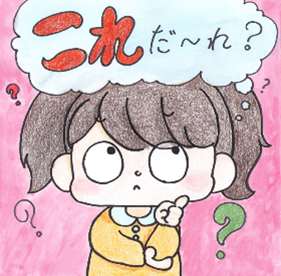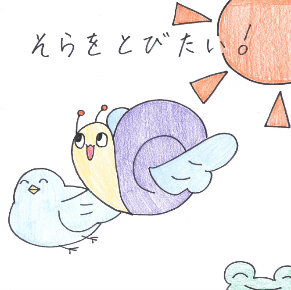- 保育科
- 2025.02.24
- お知らせ
- 2024年度名古屋短期大学保育科 創作絵本コンクールの審査結果のお知らせ
-
2024年度名古屋短期大学保育科
創作絵本コンクールの審査結果のお知らせ
応募期間 2024年7月1日~10月31日必着(※一部、延期で受理)
応募資格 対象は高校生から大学・短大・専門学校生の皆様
作品の賞 優秀賞1点 入賞2点以内 特別賞3点を選出しました。
※そのうち2点を絵本として出版し、受賞作品は賞状及び粗品を贈呈致します。
選考方法 審査員による選考 大谷学長、吉見学科長、髙野先生他保育科教員<応募者の内訳>
学内応募者97作品、学外応募者228作品 合計325作品の応募がありました。<審査の結果>
次の作品が選出されましたのでご報告いたします。優秀賞1作品、入賞2作品、特別賞は3作品となりました。なお、そのうちの2作品(「またあえたね」「ぼくはずっときみのもの」につきましては、2025年4月以降、(アマゾン等で購入できる)絵本として出版される予定です。<2025年度コンクールのお知らせ>
2025年度の創作絵本コンクールは、2024年5月頃にホームページ等からお知らせさせていただきます。なお、今年度、各高校単位でご応募いただいた先生方にはご案内のメール、郵便等でお知らせさせていただきます。
優秀賞・絵本出版候補 257番「またあえたね」
鹿本美優(しかもと みゆ)さん
愛知県立一宮高等学校2024年度2年生
書評:りすさんが食べたリンゴの種が大きな木になって出会うお話です。とてもかわいらしいりすさんの表情の変化が豊かです。パーティの風景がとても楽しそうです。りんごの木とりすさんの暖かい気持ちが伝わってきました。
入賞・賞・絵本出版候補154番「ぼくはずっときみのもの」
橋爪愛花(はしづめ あいか)さん
桜花学園高等学校2024年度卒業生
書評:幼稚園に忘れられた傘さんが、自分のお家を探すお話です。ストーリーの展開がとても自然で、空を飛ぶ風景が目に浮かびます。日常のよくある出来事を上手に空想の世界で表現しています。今度は傘を忘れないようにね。
入賞 243番「ぼくってなにいろ」
平原彩美(ひらはら あやみ)さん
愛知県立一宮商業高等学校 2024年度卒業生
書評:白色のえのぐさんが、他のえのぐと混じって新しい色を生み出すお話です。実際に白色を使うのは、なかなか難しいのに上手に表現されたストーリーになっています。子ども達も、絵の具で表現する楽しさを感じることができると思いました。
特別賞230番「これだーれ?別賞 063番「へんてこおともだち」
寺戸 咲(てらど さき)さん
愛知県立知立高等学校2024年度2年生
書評:いろいろな生き物を足元から見る視点がとても独創的な構図になっています。縦に描いた絵の描き方もユニークで、描き方に工夫を凝らしています。最後のお母さんの絵は、読み手が暖かい気持ちになります。
特別賞100番「アメのたび」
阿部 百々子(あべ ももこ)さん
愛知県立渥美農業高等学校2024年度卒業生
書評:かえるのアメくんが友達を探しに行くお話です。ヘビやタカなど怖そうな外見でも友達になれることを伝えたい作者の気持ちがこもっています。それぞれの生き物の表情も豊かに描いています。
特別賞 048番「そらをとびたい!」
神成 あみ(かんなり あみ)さん
名古屋短期大学保育科2024年度卒業生
書評:かたつむりさんが他の生き物に助けられながら、そらをとぶお話です。「やってみたい」という気持ちを大切にしたいという作者の願いが伝わる作品です。
<総 評>
本学創作絵本コンクールにご応募いただき、ありがとうございました。今回は、全体で325作品(前年度280作品)と多くの応募がありました。このコンクールも5回目になります。通常の絵本の他に、仕掛け絵本など作り方に工夫を凝らした作品の提出もありましたが、今回は受賞の候補とはなりませんでした。
作品の応募条件については、(仕掛け絵本を除いて)データを電子化することを前提としているため、本コンクールに独特の指定をしています。そのため、初めて応募される場合、戸惑う方も多いかと思います。分かりやすく説明するために、画像や動画をサイト上で発信するなどの工夫をしていきたいと思います。
評価の基準は、大枠として、描いた絵(文字含む)とストーリーで評価しています。絵が上手なだけでなく、物語のメッセージやわくわく感があったり、オリジナリティや想像性の豊かな作品を求めています。加えて、絵本として読み手である子どもの視点を捉えているかも大切にしています。絵やストーリーが子どもに伝わる中身になっているか。子どもの年齢や発達を意識して描かれているかなどです。芸術性が高いというより、保育、教育の視点が強いかもしれません。
応募された作品全体の感想としては、絵全体の色合いが薄い作品が多く感じました。淡い色も良いと思いますが、読み聞かせの場合、少し離れたところから見ることと、子どもは、めりはりのついた原色を好むので、もっと自信をもって濃い色で構成されても良いかと思いました。あと無理に教訓や知識を与えることに縛られず、のびのびと楽しみながらストーリーを考えて欲しいと思います。自分で作った絵本を子どもに読み聞かせる時、読みながら(自分が)「クスッと」笑ってしまうなら最高の作品ではないでしょうか。
この絵本コンクールは、受賞者はいますが、創作絵本の優劣を決めるのが本来の目的ではありません。あくまで、絵本作りを通して子どもの思いや、考え方、感じ方を理解して欲しいとの審査員の思いがあります。絵本作りをきっかけにして、少しでも子どもや保育に関心をもって欲しいと願っています。
末筆ですが、本学のみでなく、多くの高等学校から、「家庭科」や「総合的探求の授業」等の取り組みとして応募していただきました。ご協力いただいた大学、短大生の皆様、高校生の皆様、そして後押しをしていただいた高校の先生方にあらためてお礼を申し上げます。
今後も素敵な作品に出会うことを楽しみにしています。
2025年2月24日
名古屋短期大学保育科審査員
(代表)担当 吉見昌弘
過去の創作絵本コンクールの審査結果はこちら↓です。
2023年度名古屋短期大学保育科創作絵本コンクールの審査結果のご報告
2022年度名古屋短期大学保育科創作絵本コンクールの審査結果のご報告
2021年度名古屋短期大学保育科創作絵本コンクールの審査結果のご報告
2020年度名古屋短期大学保育科創作絵本コンクールの審査結果のご報告